私は大学時代、情緒があって心惹かれる「小路」を探し求めて、京都市内を巡って歩き回り、自らの感性のアンテナを拠り所に50近くを選出し、実測作業を通じてその魅力の解明を試みました。拙いながらも修士論文「京都における小路空間の構成に関する研究」にまとめることができました。その後当時の川崎清教授をはじめとする諸先生方によって、京都空間の研究として「仕組まれた意匠」が出版され、その中の一節に私の論文を組み入れて頂きました。
その中で特に感銘を受け印象に残っている小路空間であった「石塀小路」について、外部空間ではありますが、思いの込められた建築的空間として、今回取り上げてみたいと思います。
石塀小路は、京都東山の高台寺通りと下河原通りをつなぐ通り抜けの路地(辻子)であり、現在その一帯は重要伝統的建造物群保存地区に指定され、観光客で賑わっているようです。今では4か所からアプローチできるようですが、当時はゲートのある入り口が3か所ありました。そこから石畳が敷かれたプライベート感の漂うエリアが拡がっており、北側には石塀の続く路地に面して前庭を持つテラスハウス型の住居形態をもつ高級住宅が並び、南側には板塀で囲われた京町屋(お茶屋や料亭)が連なっていました。ここには、別世界の京都を体験できる、しっとりと落ち着いた情趣に満ちた小路空間が展開されており、幸いそれは今も残されています。
石塀小路がどのような意図で作られたのか 、その思いを理解するために、先ずこの周辺を含めた歴史背景と誕生までのプロセスを探ってみることにします。
平安時代の昔から、東山一帯は花見等で賑わって文人墨客を集め、次第に芸能文化が栄えたと聞きます。慶長年間高台寺が創建されてから、豊臣秀吉の正室北政所ねねが、山猫と呼ばれた見識が高く舞芸の達者な女たちを招き、その女性たちは高台寺の東隣に当たるこの地に集まって居を構えていたといいます。周囲には円徳院や春光院、六阿弥(安養寺の子院)といった多くの寺院なども建てられ、文化サロン風に使われることもあったようです。さらに元禄のころには、お茶屋や花街もできていたらしい。
明治時代の末期に、今でいうディベロッパー(不動産開発業者)が、かつて暴れ川であった菊渓川の下流河原で藪地になっていたところを買い取り、大正時代の初め頃に、一戸建ての借家街を造る目的で開墾を始めたようです。当時の京都の借家は10軒くらいの長屋が連なったものが一般であったので、思い切って京都の旦那衆など富裕層を対象に最高級の借家を建てることにして、北側半分を高級住宅街に、南側を席貸し(お茶屋)にと考えて開発を進めたのだそうです。その後、時に、全体の多くが席貸しになったり、旦那衆の別宅や妾宅に使われたこともあったらしい。今では、料亭や旅館、喫茶や土産物の店舗などにも利用されているようです。
実際に石塀小路に行くと、まず、誰もが通りに自由に入ることができますが、外来者の介入を拒むような私的な領域を感じます。プライバシーを守る雰囲気や機能があることが読み取れます。それは、結界を暗示する門、スケール感、奥の存在を隠すかのようにくの字に曲がった小路の構成などから生まれていると思われます。さらに、建物内部を隠す空間構成や、光沢のある石の素材感、女名前の表札、門灯などが、風情のある艶やかな様相を演出しています。また、繊細さのある高級感や格調の高い雰囲気を感じます。三層の石塀や格子戸付きの腕木門が続きますが、その構成はすべて同じですがどれにも少しずつ違いがあって、じっくり見ていくとそれぞれの個性や独自性を示しているかのようです。一見さんお断りのお茶屋筋に連なる閉鎖的な板塀には、洗練されたディテールや造作に格式の高さが窺い知れます。
歴史と文化が連綿と続く生命の流れの中で、脈々と築かれ集積された人々の営為の記憶、風土や生活感覚の機微、京都らしい美意識、秘められた自尊心、といった、目に見えない力が輻輳して作用し合い、時代の変革期における進取の気性がさらに加わることによって、今の姿が出来上がっていることが理解できます。積み重なった思いが空間形成のプログラムとなり、環境を成立させる様々なエレメントを密接に絡み合わせて再構築し、総体的な空間のアイデンティティを生み出していることがわかります。まさに、前回お話しした「holistic architecture」 と言えます。
次回は、石塀小路の空間構成の技法について考えてみたいと思います。

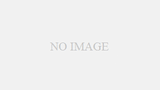
コメント