■古代エジプト文明の時代背景と世界観
周期的に起こるナイル河の氾濫が、周辺に肥沃な土壌と恵みを与える一方、天文学や測地学、幾何学など高度な知識と技術力を生みました。計画的な農業が可能となり、安定した生活を送ることができるようになり、集落が作られた。そして、神と同格とみなされたファラオ(国王)が支配する社会が完成していきました。偉大なファラオの権威を示すため、壮大な威厳の表現として、巨大な記念的建造物を造ったのです。エジプト文明は、3000年の長期スパンで、ゆっくりと発展していきました。
エジプトの宗教は、人間をはじめとする全ての生き物の霊魂は不滅であり、再生による来世を重んじるもので、死者の体に魂が留まると信じ、遺体をミイラとして保存し、将来の復活に備え副葬品と共に、ピラミッドや崖墓に安置する習慣がありました。また、村々ごとに土地の守り神がいて、太陽神ラーをはじめ、動物の顔を持つ神など、様々な神を信仰する多神教の世界でした。頂部にピラミッドを載せた先すぼまりの四角い柱状のオベリスクは、太陽神の象徴と言われています。
■ピラミッド ―量塊(マッス)の建築―
先王朝時代から死者を地中に埋葬する習慣があり、地中深くに掘られた墓室の上に、日乾煉瓦を積んだ台状のマスタバと呼ばれた墳墓が出現します。永遠なる権威を得ようとしたジェセル王は、マスタバを6段積み重ね、サッカラに石造りの階段ピラミッドを造らせました。さらに、屈折ピラミッドなどの変遷を経て、力強い単純幾何学の形に整えられ、王の来世の住まいと考える壮大な四角錐のモニュメントを築きます。
カイロの西方のギザには、紀元前2500年前後、約120年を懸けて建てられた3つのピラミッドが並んでいます。北からクフ王の第1、カフラー王の第2、メンカウラー王の第3の、3代の巨大な墳墓である。その中で最大のものがクフ王のピラミッドで、底辺が230.4m角、高さが146.6mという規模を誇る。底辺は東西南北軸に正確に揃えられ、第1と第2ピラミッドの南東の角を結ぶ延長線が、太陽信仰発祥の地ヘリオポリスの中心部に立つオベリスクを指すように計画されています。各辺の長さはほぼ等しく、立面が正方形にみえるように、地表に対し51度52分の勾配で傾斜させています。表面は上部から白い石灰岩で覆い、頂部は金箔で輝いていたといいます。ひとつひとつの石塊が、1㎥程度で平均2.5トン。どうやって積んだのかは、今なお謎に包まれたままです。ピラミッドの形状はシンプルに見えますが、実は非常に精密な構造で、高度に発達した技術の賜物なのです。
ピラミッドは単体ではなく、東面中央に葬祭神殿を建て、ナイル河流域に河岸神殿を建てるなど、複合体として建設されました。また、周辺には建設労働者や高官などが住むピラミッド・タウンがあり、農民たちにとって、河が氾濫する農閑期の大公共事業であったという説があります。食べ物やビールが振舞われ、彼らは奴隷としてではなく嬉々として働いていたことが、墓の壁画やヒエログリフ(象形文字)から読み取れます。
■神殿建築 ―軸線と柱廊の建築―
王の再生復活と永遠の生を祈る葬祭神殿は、墓所に隣接して建てられました。ハトシェプスト女王葬祭神殿は、王家の谷で知られる岩壁の屏風のように聳え立つ断崖を背後に、3段のテラスを軸線上に並べ、各テラスの高低差を列柱廊が支え、中央部を斜路でつながれています。柱廊の奥に列柱中庭、さらに奥に聖所があり、角柱、16角柱、オシリス柱など、柱を意識したデザインです。
神々に捧げる祭祀神殿は、聖域を周壁や柱廊で囲み、主軸線を参道からパイロン(塔門)を介して神殿内部に引き込み、主要室を中心軸に沿って左右対称に配置し、奥へ奥へと神の隠れた住み処へと導く構成になっており、記念性と神秘性が演出されている。屋根は石材の梁に石板を架け渡して造ったため、柱間隔が狭く、太い柱となり、その迫力に圧倒される空間となりました。柱頭は、パピルスやロータスなど、植物をモチーフとした彫刻で飾られ、後のギリシャのオーダーに継がれていきます。

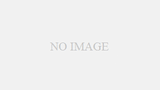
コメント