キリスト教は、約300年もの間、ユダヤ教徒と古代ローマ帝国の激しい迫害と弾圧を受け、共同墓地であった地下墓窟(カタコンベ)や裕福な信徒の住宅内で、密やかに潜伏しながら信仰が続けられた。313年、コンスタンティヌス帝(西方正帝)とリキニウス帝(東方正帝)がミラノ勅令を発布し、ようやくキリスト教信教の自由が公認されることになった。解禁された信者たちは、教義の伝道と信仰の典礼に適した独自の建築様式を作り出すことが必要となり、初期のキリスト教会堂の原空間として、集中堂式とバシリカ式の2つの形式が生まれた。皇帝も自ら、重要な教会の建設を積極的に支援した。
ベツレヘムの馬小屋での「誕生」に始まり、「洗礼」「福音宣教」「最後の晩餐とパンと葡萄酒の聖変化」「受難」「十字架上の死」「復活」「聖霊降臨」、そして「昇天」に至る、イエスの生涯における一連の主要なテーマを思い起こし、福音に従った信仰生活を送ることで、キリストとの一体化を体現する場所を求めたのでした。
まず、洗礼を授ける洗礼堂が重要であった。イエスのように、死から蘇り新しい命に生きることを再現する場所である。イエスの墓を覆うように円形プランで建てた聖墳墓教会(336年献堂)や、弾圧時代に殉教した聖人の墓廟であるマルティリウムに倣って、集中堂式聖堂が築かれた。円形や正多角形のプランの中心に祭壇や棺、洗礼槽を置き、その上部をドームで覆った。周囲に一段低い側廊を回して、屋根の段差を利用した高窓の列(クリア・ストーリー)から内陣に直接光を採りこみ、中央部を光で満たす空間構成になっている。側廊は薄暗く、求心性と上昇感の高い空間特質を持っている。円形のサンタ・コスタンツァ廟堂(350年頃)や、八角形のラテラノ洗礼堂(440年頃)などがある。
次に、バシリカ式教会堂である。イエスの生涯を追体験するミサ典礼を行う集会所が必要不可欠になった。ひとまず、古代ローマにおいて裁判や商取引などを行う集会施設であったバシリカを転用した。まず入口を入ると、周囲に列柱廊を巡らせたアトリウムと呼ばれる前庭がある。その中央に泉水亭があり、身を清めたり洗礼を受ける場所であった。その先の教会堂に入ると、初めにナルテクスという玄関廊があり、洗礼を受けキリスト教に帰依した信者でなければ、さらに奥の礼拝堂に入ることができない建物構成になっていた。
教会堂は縦長の長方形プランを採用し、信徒たちの座席が並ぶ中央の幅の広い「身廊」と、その両脇の幅が狭く天井が一段低く抑えられた「側廊」で構成された。身廊と側廊との間は円柱の列柱が並び、奥行きのある一体的な大空間になっている。こちらも、身廊と側廊の屋根の段差を利用したクリア・ストーリーを設け、ハイサイドライトを採り入れている。身廊の長軸方向の突き当り正面に、「アプス」と呼ばれる半円形の張り出しを据えている。ここはミサ典礼を司る司祭たちの座席であり、中央は司教座(カテドラ)となっている。これは、最後の晩餐のイエスと使徒たちを象徴し、カテドラの前の祭壇は、聖変化を行うための食卓を意味する。また、身廊と袖廊(トライセプト)が直交するアプス前面の交差部には、四方に横断するアーチを架け、空間に華やかな彩を加えた。半ドームの天蓋を持つアプスは、教会堂の最も重要な典礼空間であり、軸線を効かせた空間構成と、荘厳な様相を醸し出す装飾によって、信徒たちの視線が集中するように計画されている。
バシリカ式教会堂の実例としては、現存はしないが、旧サン・ピエトロ教会堂(326年頃ローマ)が挙げられる。イエスの一番弟子聖ペテロの殉教を記念して、コンスタンティヌス帝が建設した。身廊の長さが約90mもあり、両側2列ずつの側廊をもつ5廊式の巨大な教会堂で、現在のサン・ピエトロ大聖堂に引けを取らない規模を誇ったという。また、サンタ・マリア・マッジョーレ教会堂(440年頃)の身廊は、イオニア式円柱が連続して並び、木造の格天井を持つ華やかな空間になっている。
このように、求心力のある集中堂式と長軸を生かしたバシリカ式の二つの形式が、祈りの場の原初的空間として誕生し、その後のキリスト教の拡大とともに、それぞれの地域の固有な文化と結びつきながら、教会堂はさまざまに発展していくことになる。

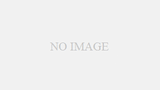
コメント