■古代オリエント文明の時代背景と世界観
ギリシア語で「二つの河」を意味するメソポタミアでは、紀元前7000年頃には、ティグリス・ユーフラテス河が作り出した肥沃で平坦な地域に、人々が定住し農耕を始めていた。前3500年頃、シュメール人が灌漑設備を整備し、都市への発展がみられる。都市には住居のほか、神殿や宮殿が建てられるようになり、「高い所」を意味するジッグラトと呼ばれる階段状の聖塔が造られた。
古バビロニア時代(紀元前2017-1595)、カッシート時代(紀元前1600頃-1155)を経て、壮大な都城や宮殿を建造したアッシリア帝国時代(紀元前744-609)、ネブカドネザル2世が新バビロン城を構え、壮麗なイシュタル門や空中庭園、バベルの塔のモデルとなったジッグラトを建てた新バビロニア時代(紀元前625-539)に続くが、古代ペルシア帝国に滅ぼされた。
石材と木材が乏しかったため、建築材料としては、粘土から始まり、次第に日干しレンガ、焼成レンガ、彩釉レンガ(タイル)へと発展していった。小さなレンガを積んで厚い壁を造り、アーチで開口部を処理し、ヴォールトで天井を覆った。アーチ構造を発明したが、原始的で型枠は用いず、レンガを傾けモルタルで接着しながら積んだ。また、床への浸水を防ぐため基壇が設けられた。
紀元前6世紀後半に、イラン高原に始まったアケメネス朝ペルシア(紀元前550-330)は、メソポタミアから小アジア、さらにアフリカ、ヨーロッパにまたがる大帝国を築いた。ペルシア人は火を尊び、拝火教を信奉した。アッシリアやバビロニアの建築技術を受け継ぎながら、イランから運んできた石材や木材を利用し、独特の巨大建築群を建造する。その代表遺構が帝都ペルセポリスの宮殿で、大帝国の富と権力を誇示するかのようであった。しかし、これらの建築も、マケドニアのアレクサンドロス大帝によって、ペルシア帝国が征服され滅亡するとともに、永くは続かなかった。
オリエント地域は、豊かな平原であるため、民族間の抗争が絶えず、興亡が繰り返された。
■ウルとバビロンのジッグラト ―高さによる表現―
紀元前2100年頃、ウル第3王朝ウルナンム王は、東北から来た遊牧民を追放し、メソポタミアの統一を果たす。首都ウルに聖域を設け、ウルの守護神で月の神ナンナのための聖塔であるジッグラトを建造した。各側壁が内側に傾斜した矩形平面の3段の基壇の上に、神祠(神の門)が建っていたとされる。底面の各頂点はそれぞれ東西南北を向き、底面の各辺や稜線は、直線ではなく外側に膨らんだ曲線を描き、視覚補正が施されている。3段目までの高さは約21m。正面とその左右にT字形に配置された大階段を持ち、各壇の側壁には、側圧による倒壊を防ぐための凹凸がつけられていた。構造体は日乾煉瓦造、外表面は天然アスファルト目地の焼成煉瓦で仕上げていた。崇高な神のための神殿は、世俗の建物を超越した記念碑性が求められ、それを高さで表現した。
紀元前6世紀頃に建てられたとされるバビロンのジッグラトは、古代ギリシアの歴史家ヘロドトスによると、最上階に神祠を持つ8層の壮大なものであった。平原の遥か彼方からも望め、神の威光を示したに違いない。傲慢な人間が天まで届く塔を建てようとした、旧約聖書の「バベルの塔」の原型とされる。
■ペルセポリス宮殿 ―列柱による表現―
王の権力の大きさは財力で決まり、神から授かるものではないという考えを持っていたため、ペルシアの王は、集めた財宝をすべて豪華絢爛な宮殿を建てるために費やし、自らの富を誇示した。紀元前518年に、ダレイオスⅠ世は壮大なペルセポリス宮殿の建設を始めた。宮殿は王の住居というよりも、属州の長官たちが王への謁見など儀式の場として使われ、帝国の象徴とされた。
山裾に位置する宮殿は、南北500m、東西300m、高さ約12mの人工基壇の上に建てられた。北西角の大階段から万国の門を経て、謁見の間であるアパダーナ、百柱の間、ダレイオス宮殿などが並ぶ。多くの柱で構成された広間が特徴的である。特に重要とみられるアパダーナは、三方に列柱廊を持つ中央広場であり、柱頭に牡牛を背中合わせにした3mもある像が彫られた高さ約19mの円柱が、6本×6列、8.7m間隔で均等に並ぶ圧巻の多柱室であった。しかし、古代エジプト建築ほどではないが、柱が広間の視界を遮っており、さらなる進展が待たれる建築技術のレベルであった。

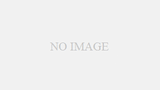
コメント